わたしたちがめざすもの
わたしたちがめざすもの
PURPOSE
- おいしくて安心な有機野菜をもっと身近なものにする
-
有機農業の技術を標準化し、
「データ活用型有機農業」として展開することで
有機農業のあしたを拓く
有機農業とは
有機農業とは、化学農薬や化学肥料に頼らず土壌本来の働きを生かすことで環境負荷をできる限り減らした持続可能な農業です。
そもそも農業は、有機・慣行を問わず、どんな栽培様式であれ環境に負荷を与えます。また、有機栽培は難しく、なかなか広まらないのも実情です。
わたしたちは、できるだけ環境への負荷の少ない栽培様式を選び、実践するとともに、持続的な経営を可能とするため栽培技術の研究・開発・普及に努めています。
有機農業の現状

有機栽培に興味がある農業者が多い
新・農業人フェアに訪れた就農希望者の調査によると、93%の方が有機農業に興味を持っていることが分かりました。
そのうち、65%が有機農業に興味を持ち、28%が有機農業をやりたいと回答しました。
この結果から、有機農業が多くの関心を集めていることが明らかです。
全国農業会議所調べ
慣行農業者の有機農業への意識と取り組み
有機農業への取り組みについて、慣行農業者を対象に調査したところ、7%がすでに取り組んでいる、または取り組む予定であると回答しました。
また、56%が「条件が整えば取り組みたい」と答えています。このことから、有機農業への潜在的な意欲の高さが伺えます。
※平成19年土地森林水産情報交流ネットワーク事業 全国アンケート調査より


有機栽培に取り組んでいる農家はまだまだ少ない
耕地面積に占める有機農業取り組み面積(2021年)
(有機JASを取得しない農地含む)
0.7%
有機農業に取り組んでいる農家の割合
(有機JASを取得しない農地含む)
0.5%
※農林水産省 農産局農業環境対策課「有機農業をめぐる事情」令和6年9月より

有機農産物への関心は高い
消費者を対象にした調査(年1回以上有機農産物を購入する人)では、99%の消費者が有機農産物に対して高い関心を示しました。そのうち、44%が現在有機農産物を購入しており、65%が「一定の条件がそろえば購入したい」と回答しています。
この結果から、有機農産物の購買意欲が非常に高いことが明らかになっています。
※農林水産省情報交流ネットワーク事業
「H19 有機農業をはじめとする環境保全型農業に関する意識・意向調査」


有機農産物の利用者は増えているが課題は残る
2022年の調査によると、有機食品を「週1回以上利用する」と回答した人は32.6%にのぼります。しかし、一方で「ほとんど利用しない」または「全く利用しない・分からない」と回答した人は57.5%でした。
これらのデータは、有機食品の利用者が増加している一方で、まだ多くの人が日常的に利用しているとは言えない現状を示しています。
※農林水産省「有機食品市場規模及び有機農業取組面積の推計手法検討プロジェクト」から、農業環境対策課作成

有機農産物の購入価格と求められる条件
流通加工業者と消費者が有機農産物を購入する際の価格について、調査結果は以下の通りです。
- 1割高までなら購入したい:44.9%
- 2〜3割高までなら購入したい:27.5%
- 同じ価格なら購入したい:21.7%
- 4〜5割高以上でも購入したい:2.3%
これにより、有機農産物の価格が購入意欲に大きく影響することが分かります。
消費者が有機農産物を購入する上で求める条件
- 表示が信頼できること:72.9%
- 近所や買いやすい場所で販売されていること:70.3%
- 価格がもっと安くなること:68.0%
- 味や栄養価が優れていること:50.6%
- 見た目が整っていること:3.3%
- その他:2.6%
- 無回答:0.3%
これらのデータは、有機農産物の普及において、価格や販売場所の改善が重要な課題であることを示しています。
※平成27年度農林水産情報交流ネットワーク事業調査結果より
有機農業の課題
栽培が難しい
しかし、栽培の難しさゆえに、なかなか広まらないというジレンマがあります。
慣行栽培は、長年のデータの実績もあり、栽培上で起ここる問題(病害虫など)と対策が明確に対応しており、栽培技術が体系化されているため、失敗しにくい栽培方法です。
対して、有機栽培は、栽培技術が複雑系(問題に対しての対策は総合的・全体的に考える必要がある)で体系化されていないため、個人のカンコツ経験によるところが大きく、栽培が難しいのが現状です。

有機農産物の悪循環
有機農産物の市場には、以下のような悪循環が存在しています:
- 生産者が安定せず、生産量が少なくなる
- 生産量が少ないことで価格が高くなる
- 価格が高くなることで消費者が購入を控える
- 消費者が少ないことで売り先が少なくなり、市場が狭くなる
- 市場が狭くなることで、生産者の活動がさらに安定しなくなる
この循環を断ち切るためには、生産・流通・消費者の各段階での連携と適切なサポートが必要です。
有機栽培に取り組む生産者は少ない
有機野菜は希少で、消費者にとっては身近ではない
有機農業のあしたを拓く
オーガニックnicoの取り組み
有機栽培の技術を体系化し
有機農業の悪循環を好循環に変える
データ活用型の有機農業
- 定量的な
計測人の観測⇨データ化 - 判断基準の
設定人の感覚⇨標準値 - 判断基準に
基づいた
アクション判断のばらつきが補正

有機農産物の好循環
有機農産物の市場において、以下のような好循環を形成することが理想とされています:
- 生産性の向上により生産量が増加する
- 生産量が増加することで手ごろな価格での販売が可能になる
- 手ごろな価格により消費者の購入意欲が高まる
- 消費者が増えることで市場が拡大し、販売先が増える
- 市場拡大により生産者の活動が安定し、さらに生産性が向上する
この循環を実現するためには、生産・流通・販売における効率化と連携が求められます。
有機農業の収納者が増え、環境負荷の小さい持続可能な農業が広まることで
ひとと地球の健康につながるおいしい野菜があたりまえに食卓に上がる社会をつくる
2525(ニコニコ)運動
オーガニックnicoは創業以来、国内有機農産物のシェアを25%まで引き上げ、有機農産物をあたりまえにしようという2525(ニコニコ)運動に取り組んでいます。
社名のnicoはここからきています。
この取り組みの中で、地球環境のこと、地球に暮らす隣人のこと、食のこと、生きることについて、考え行動する人が増えていくことを願っています。
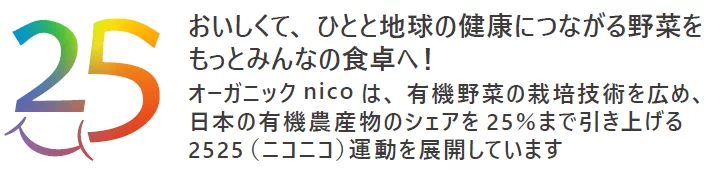
おいしくて、ひとと地球の健康につながる野菜をもっとみんなの食卓へ!
オーガニック nico は、有機野菜の栽培技術を広め、日本の有機農産物のシェアを25%まで引き上げる「2525(ニコニコ)運動」を展開しています。
